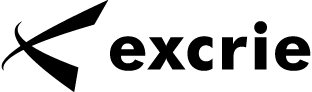ワーママの8割が時間貧困だったことがわかる【別冊よげんの書―Wの時代~ママ市場の歩き方を考える:よげん3】
2023.01.23
聞く技術研究所
生活の変化や経済・環境の変化など、社会課題を背景に少し先の生活を考えるためのマーケティングセミナー「月刊:よげんの書」の別冊版として、「Wの時代 ~ ママ市場の歩き方を考える」を開催しました。ママ市場は、出産・育児支援や職場・家庭内のジェンダーバランスの見直し、メンタルヘルスへの取り組みなど、今最もサポートや注目が集まっている分野です。
セミナーでは妊娠・子育て期の女性の現状や課題、これから取り組むべきマーケティングについてお伝えしました。今回の記事では、セミナーで発表された内容をご紹介します。
ワーママの8割が時間貧困だったことがわかる
日本人は全体的に時間貧困が際立つ
経済協力開発機構(OECD)のデータベースによると、日本はG7のうち有償労働が最も長い363分で、2位のカナダ305分と一時間近くも差があった。一方で、子どもや個人のケア、余暇に充てる時間は最も少なかった。日本人の家事・買い物・家族のケアが短いことについて、立命館大学の筒井淳也教授は「働く時間が長い分、短い時間で集中的に家事・育児をこなす必要があり、負担が重い」と解釈する。日本人は時短、タイパ(タイムパフォーマンス)をしなければいけない状況だというのが分かる。
共働きの3割が時間貧困で子育て世代を苦しめている
時間の余裕のなさを示す「時間貧困」が6歳未満の子どもを育てる世代を苦しめている。正社員の共働き世帯の3割が、十分な育児家事や余暇の時間をとれない状況に陥っているのだ。妻と夫で分けると、妻の80%が時間貧困だったのに対し、夫は17%。女性の方に大きくしわ寄せがいってしまっている。海外は家事の外注等があるが、日本の女性は家事の外注に罪悪感を覚えやすいとされており、それも時間貧困になってしまう一因になっているだろう。生活時間に余裕がなければ子どもを多く育てるのは難しい。少子化を加速させないためにも、男性の家事参加はもちろん、働き方の見直し、家事の一層の支援が喫緊の課題となっている。
時間貧困がマミーギルトにつながる。7割が罪悪感を感じる
母親が子どもや家庭に抱く罪悪感のことをマミーギルトと呼ぶ。現代は収入が増えにくい中、子どもの教育など求める生活水準は上がり、女性が出産後も正規雇用にとどまり共働きを続けないと、豊かな生活がしづらい時代だ。コロナ後は7割もマミーギルトを抱える状況になっている。罪悪感を自ら手放そう、という動きも生まれている。自分が幸せになれる方法を主体的に考えることが大切だ。
時短やタイパの取り組みや提案、商品などはたくさんある。それらは時間は短縮できるが、罪悪感の貢献には貢献していないのかもしれない。手をかけていないと罪悪感を感じる人もいる。母親のマミーギルト解消のためには、ゆっくり丁寧にお掃除、料理を作れる商品やサービスなど、納得して、満足して家事ができるものを用意するのも大事だろう。また。手を抜いていいんだよ、という姿勢を伝えるのも必要だ。そんな視点もママ市場のマーケティングには必要だ。
1日は24時間しかないので、働く時間が長ければ、他の時間は短くならざるを得ない。トレードオフだ。正社員で居続けるためには、長い時間働く必要がある。パートアルバイトは、女性の能力を生かし切れていない職種しかない。なので、当然収入は低くなる。正社員、非正規であっても、自由に働き方を選べて、同一労働、同一賃金があれば、ゆとりのある生活になるのではないか。
時間がないから、家事を一生懸命できないことで罪悪感を抱える人は多い。当たり前にチクチクとした罪悪感を抱えている。とくに、ワーキングマザーは子どもを預けて、泣くと自分も泣くことを重ねている人もいる。ただ、家族の意識や声がけで大分違う。
時間を埋めるには、手伝ってもらう必要がある。昔は三世代でおじいちゃんおばあちゃんが手伝ってくれた。現在はその家族形態は難しいので、アウトソーシングして、家事を頼む必要がある。だが、それはハードルが高い。
ママレディでも家事代行をオススメしたが、アンケートをとったところ「知らない人が家に入るのは嫌だからダメ、と旦那が言っている」という声もあった。「家事は主婦の仕事。なんでお金を払ってやってもらうのか」という意見を持っている男性もいる。夫婦はパートナーで、一つの共同事業を行っているので、手伝う、ではなく、一緒にやる、という意識が大事。
-
Download
各種サービスのご紹介資料のダウンロードは、こちらからお願いします。
-
Contact
各種サービス、調査結果の利用等に関するお問い合わせやご相談は、こちらからお願いします。